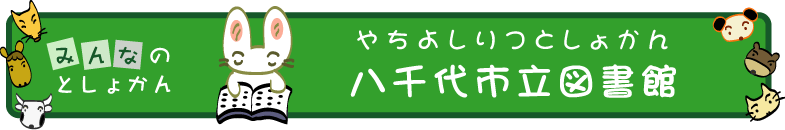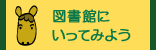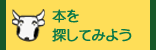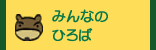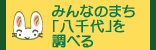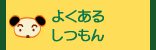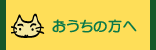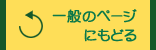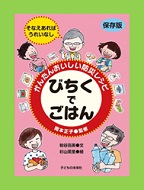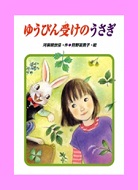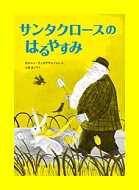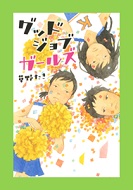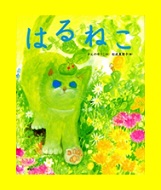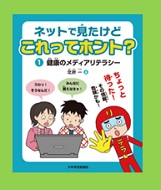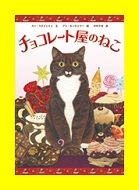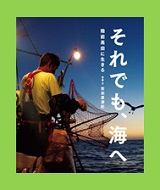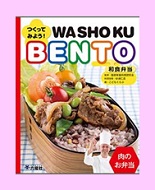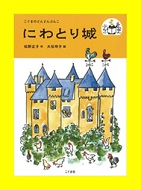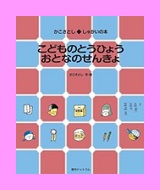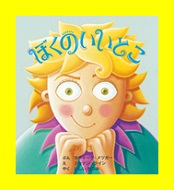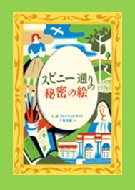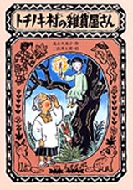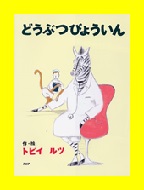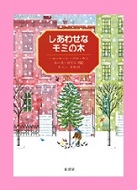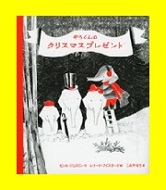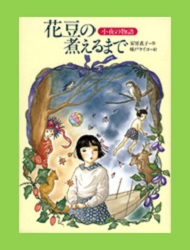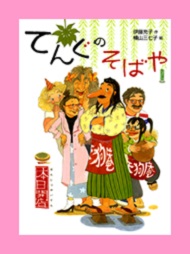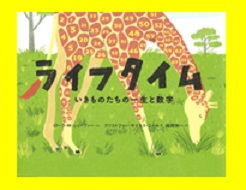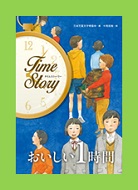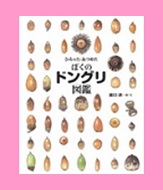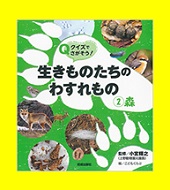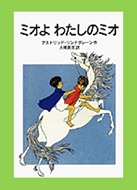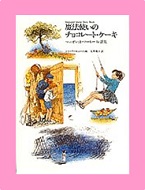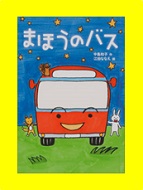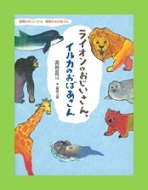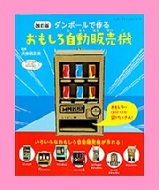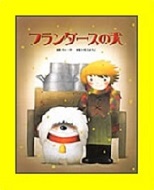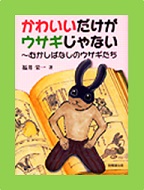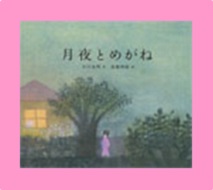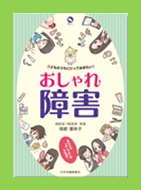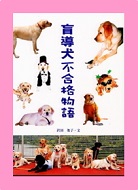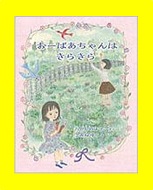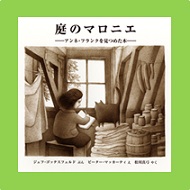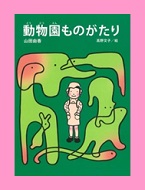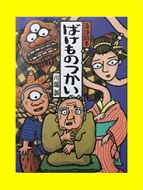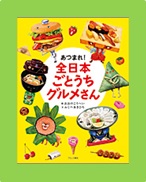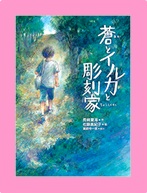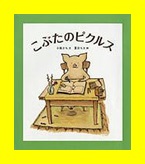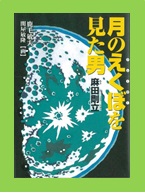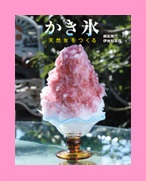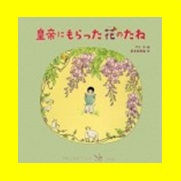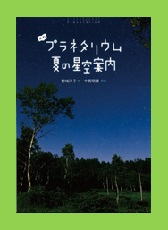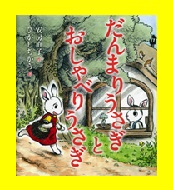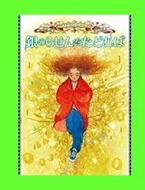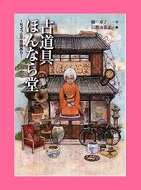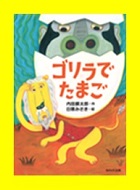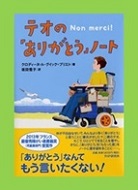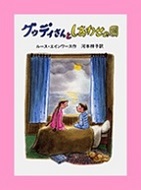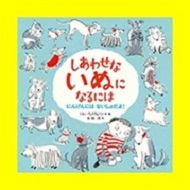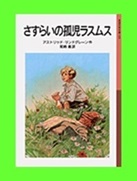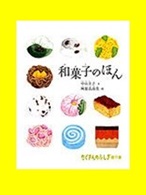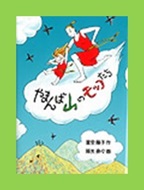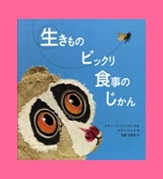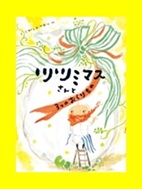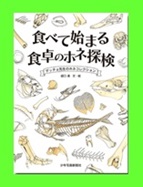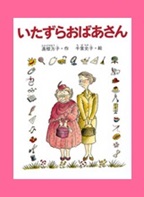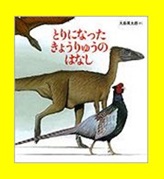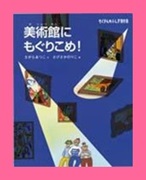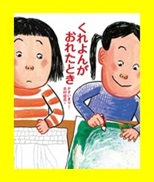『びちくでごはん ~ かんたんおいしい防災レシピ ~ 』 粕谷亮美/文,岡本正子/監修,杉山薫里/絵,子どもの未来社,369/カ
「びちく」というのは、将来(しょうらい)や万が一の場合に備えてたくわえておくこと、またそのたくわえのことです。わたしたちのまわりでは、大きな災害がいくつも起こっています。いつ起こるかわからない災害にそなえて準備しておくことは、とても大切です。この本には、災害が起こった時にかんたんにできるおいしいごはんの作り方や、ラップやポリぶくろなどを使った、調理の工夫などが書かれています。
「そなえあればうれいなし」です。家族で、このびちくごはんをためしてみるといいかもしれません。(緑が丘図書館)
『ゆうびん受けのうさぎ』 河俣規世佳/作,狩野富貴子/絵,あかね書房,913/カ
夏子はもうすぐ4年生。引っこしてきた新しい家の、うさぎもようのゆうびん受けがとても気に入りました。新学期が始まり、るすばんをする夏子は、さびしくお母さんを待っていました。ゆうびん受けのうさぎは、夏子をみかねて、ゆうびん受けからとびだし、声をかけました。夏子とうさぎは友だちになり、毎日おやつを食べながらおしゃべりしました。ある日、お友だちの家に行く夏子に、うさぎは「雨がふるよ」と教えてくれました。いいお天気だったので、うさぎのいうことがしんじられず、夏子はうさぎとけんかをして家を出ました。でも、友だちと遊んでいると雨がふり始めました。
ゆうびん受けのうさぎが、夏子のことを手助けするふしぎなお話です。(緑が丘図書館)
『サンタクロースのはるやすみ』 ロジャー・デュボアザン/ぶん・え 小宮由/やく,大日本図書,933/デ
はるになっても、サンタクロースのすむほっきょくは、いちめんのゆきでした。サンタクロースは、はるの花を見たり、ことりのさえずりをきいたり、はるの日ざしの中をさんぽしてみたいとおもっていました。そこで、おもちゃづくりをちょっとだけ休んで、はるやすみをとることにしました。しょうたいをかくして町にでかけ、さんぽをたのしんでいると、小さな女の子から、「このおじいさん、サンタクロースからおひげとあかいはなをぬすんじゃった」といわれてしまいました。サンタクロースはおもわず「わしはサンタクロースじゃ」とさけび、町はおおさわぎになりました。
さて、サンタクロースのはるやすみは、どうなってしまうのでしょう?(緑が丘図書館)
『グッドジョブガールズ』 草野たき/著,ポプラ社,913/ク
六年生のあかりには由香(ゆか)と桃子(ももこ)という「悪友(あくゆう)」がいます。悪友だから、「仲良し」みたいにマジで心配したり、本音を言ったりしないで、ふざけてジョークでおしまいにしてしまいます。あかりは、この関係を楽しんでいたけれど、だんだん二人と「仲良し」とか「親友」になりたいと思うようになりました。小学校生活の思い出づくりに、チアダンスをすると決めた三人。でも、おたがいの気持ちがぶつかりあって…。
あかりの思いがむねいっぱいに伝わり、三人を応援(おうえん)したくなります。(緑が丘図書館)
『都道府県のかたちを絵でおぼえる本』 造事務所/編,実務教育出版,291/ト
都道府県(とどうふけん)は、それぞれ、いろいろな形をしています。いつも「県」として見ている形も、回転させたり、じっくり見たりすると、全くちがったものに見えてきます。たとえば、わたしたちの住んでいる千葉県も、90度回転させると、べつの県のように見えてきますし、チーバくんとして見なれている形も、じっくり見るとインコにも見えてくるようです。また、それぞれの都道府県のれきしや、かんきょう、豆ちしきも書かれていて、今までしらなかった県のことが、よくわかります。
じっくりと本を見て、それから日本地図を見てみてください。もう、地図が“絵”にしか見えないかもしれません。(緑が丘図書館)
『はるねこ』 かんのゆうこ/文,松成真理子/絵,講談社,E/マ
去年(きょねん)のはる先のころ、あやが「はやくあったかいおそとであそびたいなあ」とおもいながら、おりがみあそびをしていると、にわで、わか草いろのねこがさがしものをしていました。ねこは「ぼくは、はるねこ。はるをはこぶのがぼくのしごとなの。でもたくさんの“はるのたね”をおとしちゃったんだ」といいました。あやは、それで、はるがこないのだとわかりました。あやとはるねこは、たのしくうたいながら、おりがみでたくさんの花をつくりはじめました。すると…。
あたたかなやさしいえで、はるいっぱいのえほんです。(緑が丘図書館)
『ネットで見たけどこれってホント? 1』 北折一/著,少年写真新聞社,361/キ
メディアとは、ネット、テレビ、新聞など情報が流通する媒体(ばいたい)のこと、リテラシーとは情報を活用する能力のことです。もし何か知りたいことがあったとき、パソコンやスマートフォンでネット検索(けんさく)すれば、数秒で、ほしい情報をとても簡単(かんたん)に手に入れることができます。しかし、情報をだれでも自由に発信できるネットの世界では、いかにも真実かのような情報が全くのウソであることもめずらしくありません。この本では、ネットで見かける「これって本当なの?」と思ってしまう情報を取り上げ、どう考えれば良いかをガイドします。
1巻(かん)では、インフルエンザやダイエットなど「健康」に関すること、2巻では「食」、3巻では「生活」に関することを集めています。(緑が丘図書館)
『ちびドラゴンのおくりもの』 イリーナ・コルシュノフ/作,酒寄進一/訳,伊東寛/絵,国土社,943/コ
ハンノーは、「デブソーセージ」っていわれるから、学校が大きらいです。ある日、学校の帰りに出会ったちびドラゴンを家につれて帰りました。ちびドラゴンはだんろの火をおいしそうに食べます。ハンノーが、おやつのチョコレートのかけらを火の中に入れてやると、ペロリ。「ウーン、これはうまい!こんなにおいしい火を食べるのは生まれてはじめてだ。チョコレートの火はさいこうだ。」ちびドラゴンとハンノーは友だちになり、遊んだり、学んだりして、いっしょにすごします。ドラゴンの学校では落ちこぼれだったちびドラゴンは、ハンノーをはげまし、ほめてくれます。ハンノーは少しずつ自信(じしん)を持っていきます。ちびドラゴンのおくりものって何だったのでしょうか?(緑が丘図書館)
『チョコレート屋のねこ』 スー・ステイントン/文,アン・モーティマー/絵,中川千尋/訳,ほるぷ出版,E/モ
ちいさな村のチョコレート屋(や)さんに、おじいさんとネコがくらしていました。これといった名物(めいぶつ)はなく、しずかでたいくつな村のため、チョコレート屋にもおきゃくさんはめったにきません。ある日、おじいさんはチョコレートねずみをつくってみました。ねこがちょっぴりかじってみると、なんておいしいのでしょう。「こんなにおいしいんだもの、だれかに、たべてもらわなくちゃ。そうだ!」ねこは、店(みせ)をとびだしました。ねずみのチョコレートがめぐりめぐって、いろいろな人とつながっていくのはまるでまほうのようです。たくさんのチョコレートとネコが、とてもきれいな絵(え)でえがかれていて、絵本のせかいにひきこまれます。(緑が丘図書館)
『それでも、海へ ~ 陸前高田に生きる ~ 』 安田菜津紀/写真・文,ポプラ社,369/ヤ
岩手県陸前高田市の漁師 菅野(すがの)修一さんは、みんなから“じっちゃん”とよばれています。2011年3月11日の東日本大震災(しんさい)の時、大きな地震がおこり、見たこともないような
大きな黒い波が、じっちゃんのくらす町をのみこんでいきました。ほとんどの船や家が流され、つなみにさらわれてなくなった人もいました。変わり果てた町のすがたを目の当たりにして、じっちゃんは「もう海に出るのはやめよう」と思いました。でも、孫のしゅっぺの「じっちゃんのとってきた白い魚をもう一回食べたい」という言葉を聞いて、じっちゃんはハッとしました。そして、再び海に出ることを決心しました。じっちゃんは、今日も船に乗って漁に出かけます。
東日本大震災から6年。つらく悲しい思いをむねに復興を目指している人々のことを、わすれないでいたいですね。(緑が丘図書館)
『つくってみよう!WASHOKU BENTO1 ~ 肉のお弁当 ~ 』 服部栄養料理研究会/監修,こどもくらぶ/編,六耀社,596/ツ
いつもは作ってもらうおべんとうを、自分で作ってみましょう。
この本では、「和食」のりょう理人が、「和食」のワザや味、くふうを活かしたおべんとうの作り方をやさしく教えてくれます。やさいなどを美しく見せる“かざり切り”や、いろどりを考えたもりつけ方など、和食の豆ちしきもいろいろとしょうかいされています。
本で、「和食のきそ」を一通り学んだら、おべんとうを作って、家族や友だちとみんなで味わってみましょう!けがをしないように気をつけてくださいね。(緑が丘図書館)
『にわとり城』 松野正子/作,大社玲子/絵,こぐま社,913/マ
むかしむかし、びんぼうでのろまだけど、こころのやさしいおひゃくしょうのむすこがいました。おひゃくしょうがなくなり、1人のこされたむすこは、すむいえもなくなってしまい、1羽(わ)のめんどりとたびにでます。1人と1羽はあるきつづけて、まよいこんだまっくらな森の中で夜(よる)のまものとでくわしました。なぞなぞにこたえられなければ、むすこをとって食(く)う、という夜のまものあいてに
むすことめんどりはいっしょに立ちむかいます。
イラストがたくさんあって、とてもよみやすい本です。(緑が丘図書館)
『使って覚える記号図鑑 ~教科書に出てくる科学の記号・身近なマーク大集合!~』 白鳥敬/著,誠文堂新光社,801/シ
わたし達のまわりには、記号やマークがあふれています。算数の計算記号や、単位、地図記号、音ぷも記号です。天気予報に出てくる天気記号や、道路の交通標識、メールの絵文字・顔文字も記号です。記号は、言葉で説明するよりわかりやすく、明確に、その意味を伝えることができます。また、世界共通の記号であれば、世界中のだれもが、記号の意味を理解することができます。この本で、いろいろな記号と、その記号の持つ意味を見てみましょう。
本の中の「やってみようクイズ」にも、ちょう戦してみてください!(緑が丘図書館)
『こどものとうひょう おとなのせんきょ』 かこさとし/著,復刊ドットコム,314/カ
じどう館前の広場は、たくさんの子どもが遊んでいるので、けんかやもめごとがしょっちゅう 起こっていました。そこで、みんなは、大人のせんきょのまねをして、とうひょうで広場の使い方を決めることにしました。とうひょう数が一番多かったのは野球で、広場は野球チームが使うことに決まりました。多数決で決まったからと、みんなは広場が使えなくてもがまんしましたが、本当は広場で遊びたいと思っていました。そのうちに、また、もめごとが起こりだしました。
せんきょやとうひょうなんて、自分たちにはかんけいないや!と思ったかもしれません。でも、みんなも、18才になったら、せんきょけんというけんりがもらえ、大人と同じようにせんきょでとうひょうすることができるのです。 この本を読んで、せんきょ、とうひょうなどについて、考えてみましょう。(緑が丘図書館)
『ぼくのいいとこ』 スティーヴ・メツガー/ぶん,ジャナン・ケイン/え,いしいむつみ/やく,少年写真新聞社,E/ケ
じぶんの「いいとこ」は、どんなところでしょう?「いいとこ」より、わるいところ、きらいなところが、たくさんうかぶかもしれませんね。この本では、子どもたちが、じぶんの「いいとこ」を、じしんをもってはなしてくれています。みんなも、じぶんのことをよーくかんがえてみてください。やさしいところ、げんきがあるところ、おもいやりがあるところ、ちゃんとあいさつできるところ。「いいとこ」がいっぱいみつかるかもしれません。その「いいとこ」は、みんながどんなじぶんになりたいのかを、おしえてくれています。じぶんの「いいとこ」をたいせつにしていってくださいね。(緑が丘図書館)
『世界にたったひとつ君の命のこと』 奥本大三郎/著,世界文化社,461/オ
みなさんは、命とは何か、命はどこにあるのか考えたことがありますか?
たとえば、ロボットが故しょうしたら、修理をします。修理できなくなったらすてて、また新しいものを造ります。けれども人間は、けがをしたら自然に治る力があります。ロボットにはこんな能力がありません。命ある人間とロボットのちがいです。
こうして、ひとつひとつ考えていくことによって、命はなぜ大切にしなければならないのか、少しずつ解ってきます。
日本のファーブル・奥本大三郎(おくもとだいざぶろう)先生がやさしく温かい言葉で語りかけています。(緑が丘図書館)
『もしも日本人がみんな米つぶだったら』 山口タオ/文,津川シンスケ/絵,講談社,611/ヤ
いつも食べている白いごはん。よく見るとお米の一つ一つは小さなつぶだけど、お茶わん1ぱいに、何つぶのお米が入っているか考えてみよう。数えようとしても、ごはんつぶはくっついている。どうすればいいでしょう?!
そんな時はお米の国から来た米とのさまの出番。お米の国の秘伝(ひでん)を教えてくれるそうですよ。いっしょに工夫しながら数えてみると、その数はなんと、やく4000つぶ。では、米つぶ1つぶが人間ひとりだとすると、学校のじどう全員の数はお茶わん1ぱいにはほど遠く、東京の人口はお茶わん3000ぱい!
そうやって数について考えてみるのが、お米の国の秘伝、“米つぶ換算術(かんさんじゅつ)”。米とのさまといっしょに、お米と数について考えてみましょう!(緑が丘図書館)
『12にんのいちにち』 杉田比呂美/作,あすなろ書房,E/ス
あさ6じ。おきる人、もうしごとをしている人、これからねむる人。1日のすごしかたは人それぞれです。
この絵本(えほん)は、ある町の12人の1日をたどる絵本です。とうじょうするのは、サッカー少年(しょうねん)、町にある銅像(どうぞう)、看護師(かんごし)さん、パンやさん、動物園(どうぶつえん)のライオン、赤ちゃんなど。かれらの24時間(じかん)を2時間ごとにたどりながら町を1しゅうします。
ささいなことから、大じけんまで!おこっていることを、よーくみてたくさん見つけてみてください。
さて、きょうはどんな1日になるでしょうか?町の中でのこうりゅうや、おどろきのつながりなど、小さな発見(はっけん)がたのしめる絵本です。(緑が丘図書館)
『スピニー通りの秘密の絵』 L.M.フィッツジェラルド/著,千葉茂樹/訳,あすなろ書房,933/フ
美術館で働いていた祖父・ジャックのもとで、ニューヨークのメトロポリタン美術館を庭のようにして育ち、美術に精通した少女、セオ。
彼女の人生は、ジャックが事故でとつぜん亡(な)くなったことにより、大きく変わっていきます。
「卵(たまご)の下を探(さが)すんだ―手紙が……それと、宝物(“トレジャー”)」
ジャックが最期にのこした言葉から、みつかる一枚の絵画。
手がかりを見つけるたびになぞが深まるばかり。
セオがセレブ女子ボーディといっしょに秘密(ひみつ)の絵の真相にせまる!
秘密の絵画をめぐる美術歴史ミステリーです。 (緑が丘図書館)
『トチノキ村の雑貨屋さん』 茂市久美子/作 ,二俣英五郎/絵,あすなろ書房,913/モ
トチノキ村には、たった1軒(けん)小さなお店があります。
名前はマルハナ商店、サクラさんのお店です。
おかしや生活にひつようなものは、たいがいそろっています。
木の葉がめぶきだすころ、小がらなむすめさんがロウソクの灯心(とうしん)を買いにきました。
サクラさんは、お代にお金ではなく、ミツバチのすで作ったロウソクを受け取りました。
その夜、サクラさんがロウソクに灯(ひ)をともすと、あまいにおいがただよい、「あの子はきっと、トチノキ山の山の精(せい)なんだ」と思いました。
マルハナ商店に、カッパやキツネやタヌキなど、ふしぎなお客がおとずれる、六つのお話が楽しめます。
(緑が丘図書館)
『どうぶつびょういん』 トビイルツ/作・絵,PHP研究所,913/ト
「どうぶつびょういん」といっても、どうぶつのためのびょういんではありません。
なんと、かんじゃさんは子どもたちで、おいしゃさんがどうぶつたち!
ここは、どうぶつえんのとなりにある、どうぶつのおいしゃさんたちが、子どもたちのわるいところを
なおしてくれるびょういんです。
やさいがきらいで元気(げんき)がない女の子には、ブタさんのかぞくがおいしゃさん。
学校のじゅぎょうがたいくつでぼーっとしてしまう男の子には、ウサギさんがおいしゃさん。
ほかにもキリン、モグラ、ペリカンなど、たくさんのどうぶつがでてきてかつやくします。 (緑が丘図書館)
『銃声のやんだ朝に』 ジェイムズ・リオーダン/作,原田勝/訳,徳間書店,933/リ
1914年、第一次世界大戦という大きな戦争が起こっていました。
多くの男達が、国のため、家族のために兵士となって戦いました。
ヨーロッパの西部戦線では、はげしい戦いの中、多くの若い兵士が命を落としていました。
しかし、クリスマスの朝、奇跡(きせき)のような出来事が起こります。
いつもは敵として戦っているドイツ軍とイギリス軍の兵士達が、クリスマスを祝うために、戦いを一時止めて、サッカーの試合を行ったのです。
きびしい「戦争」の現実、命の尊さ(とうとさ)、信仰(しんこう)に対する思いなどが、強く感じられるお話です。
(緑が丘図書館)
『しあわせなモミの木』 シャーロット・ゾロトウ/文,ルース・ロビンス/絵,みらいなな/訳,童話屋,933/ゾ
近所の人からかわり者と思われているクロケットさん。
クリスマスイブの夕方、クロケットさんは、店のおくから、だれかがよんでいるような気がして、花屋の店先に立ちどまりました。
クロケットさんをよぶように立っていたのは、かれかけた小さなモミの木でした。
クロケットさんは、このモミの木を大切に育てました。
そして、ある年のクリスマス。大きく育ったモミの木は、とても美しいクリスマスツリーになりました。
「生きているものたちは、みんなおたがいに気持ちが伝わる…」ということを知っていたクロケットさんとモミの木の、おだやかで心あたたまるお話です。
(緑が丘図書館)
『ぞうくんのクリスマスプレゼント』 セシル・ジョスリン/作,レナード・ワイスガード/絵,こみやゆう/訳,あかね書房,E/ワ
クリスマスイブの夜(よる)、ぞうくんは、かぞくのみんなに「ひみつのねがいごとってある?」ときいてまわりました。
おかあさん、おとうさん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなそれぞれ「ひみつのねがいごと」をはなしてくれました。
でも、みんなの「ねがいごと」は、ぞうくんがききたかったことと、ちょっとちがっていました。
ぞうくんは、みんなにクリスマスプレゼントにほしいものをききたかったのです。
この本には、ぞうくんのかぞくをおもうやさしい気もちと、かぞくのぞうくんをおもうやさしい気もちがあふれています。
本をよみおわったあと、かぞくやおともだちに、プレゼントをあげたい気もちになるかもしれません。
(緑が丘図書館)
『花豆の煮えるまで ~小夜の物語~』 安房直子/作,味戸ケイコ/絵,偕成社,913/ア
小夜は、山の温せん宿の一人むすめです。
お母さんは、山の精・山んばで、小夜を産むと山の風になって山んばの里に帰って行きました。
小夜にも山んばの不思議な力があって、風になって山をかけめぐったり、おにの子と遊んだりします。
ある時、朴(ほう)の木の精・ホウノキさんが、小夜の一番いいリボンをくれたら、お母さんに会わせてあげると約束してくれました。
そこで、小夜は大切なリボンを何本も朴の木に結びました。
けれども、ホウノキさんは木の中でじっとだまっています。
切ない小夜の気持ちが、空に広がっていきます。
この本には、小夜の不思議なお話が六話入っています。(緑が丘図書館)
『てんぐのそばや ~本日開店~』 伊藤充子/作,横山三七子/絵,偕成社 ,913/イ
なみ木通りに、そばや「天狗庵(てんぐあん)」ができました。
店の主人は、大きな鼻のてんぐで、そばを打つのが上手です。
てんぐは“自慢屋(じまんや)”で、自慢を始めると、鼻の中の「自慢バチ」がぶんぶんさわぎだし、鼻がどんどん大きくなります。
てんぐは、お店を開けましたが、さっぱりお客さんが来ません。
そこで、ポスターを書いたり、となりのクリーニング屋さんにのれんを作ってもらったりしました。
さあ、天狗庵にお客さんは来てくれるのでしょうか。(緑が丘図書館)
『ライフタイム』 ローラ・M.シェーファー/ぶん,クリストファー・サイラス・ニール/え,福岡伸一/やく,ポプラ社,E/ニ
虫やどうぶつが、生まれてからしぬまでのじかんをしらべてわかった「かず」の本です。
一生のあいだにトナカイのつのは、なんかいはえかわるかな?
キツツキは、木になんこあなをあけるかな?
カンガルーのメスはなんびきの赤ちゃんを生むのかな?
ページをめくりながら、生きものたちの一生にかくされた「かず」のふしぎをたのしんでください。(緑が丘図書館)
『おいしい1時間』 日本児童文学者協会/編,中島梨絵/絵,偕成社,913/オ
コンビニの駐車場(ちゅうしゃじょう)であやしいおじさんによびとめられた。
「お金ほしくない?」
おこづかいが少なく、まだ買っていない新しいゲームを友達にじまんされたばかりのぼくの心は大きくゆれていた。
なにもしなくていい、1日1時間だけ君の時間をもらう、それだけで1日千円手に入る。
そんなおいしい話に、うたがいつつもぼくは飛びついた。
きみょうな『おいしい1時間』の他、「1時間」にまつわるお話が5つはいっています。(緑が丘図書館)
『ひろった・あつめたぼくのドングリ図鑑』 盛口満/絵・文,岩崎書店,657/モ
学校に行くとちゅうや、家のまわりに落ちているドングリ。
丸いものや細長いものなど、色や形もいろいろですね。
みんなの家のまわりにあるドングリは、どんな形をしていますか?
「ブナ科」の木になる実は、みんな「ドングリ」といい、日本には、やく17しゅるいあると言われています。
同じような形のドングリでも、もしかしたら、それぞれちがう木のドングリなのかもしれません。
この本を見て、身のまわりのドングリは、何の木のドングリなのか調べてみましょう!(緑が丘図書館)
『クイズでさがそう!生きものたちのわすれもの ②森』 小宮輝之/監修,こどもくらぶ/編,佼成出版社,481/ク
<
森の中には、足あとやたべのこし、フンなど、生きものたちがのこした「わすれもの」があります。
いろいろな「わすれもの」からは、生きものたちが、どんなくらしをしているのかがわかります。
この本は、そんな生きものたちの「わすれもの」が、クイズになっています。
クイズで、生きものたちのことをしり、「わすれもの」をさがしにいってみましょう!
あたらしいはっけんが、いっ
ぱいあるかもしれません。
『クイズでさがそう!生きものたちのわすれもの』というシリーズの2かん目の本です。
(緑が丘図書館)
『ミオよわたしのミオ』 アストリッド・リンドグレーン/作,大塚勇三/訳,岩波書店,949/リ
みなしごで9才の男の子は、ある日「はるかな国」に迷いこみます。
はるかな国の王様は、男の子の本当のお父さんで、男の子は「ミオ」という名前でした。
ミオは、お父さんといっしょに遊んだり、おしゃべりをしたり、ユムユムという友だちもでき、楽しい毎日を過ごしていました。
そして、ある時、子どもをさらっていく残こくな騎士(きし)、ガトーと戦うため、ミオとユムユムは白馬に乗り、「暗い森」へ出かけます。
にげこんだ暗いほらあなで、ユムユムとはぐれてさびしくなげくミオに、お父さんの声が聞こえてきました。
そこで、ミオは元気を出し、おそろしいガトーの城(しろ)へ向かいます。
リンドグレーンの明るく楽しい作品が多い中で、この本は、民話のようなふしぎな物語です。
(緑が丘図書館)
『魔法使いのチョコレート・ケーキ』 マーガレット・マーヒー/著,石井桃子/訳,シャーリー・ヒューズ/画, 福音館書店,933/マ
あるところに、魔法(まほう)よりも料理(りょうり)のほうがとく意な魔法使いのおじいさんがいました。
魔法使いのおじいさんは、じまんのチョコレート・ケーキを子どもたちにごちそうしたいと思い、町中の子どもたちに招待状(しょうたいじょう)を送りました。
でも、子どもたちは、おじいさんを悪い魔法使いだと思っていたので、だれもきませんでした。
それから何年も何年も後、どこからかにぎやかな声が聞こえてきました。
ふしぎとおどろきがいっぱいの物語が8つと、詩が2つ、はいったおはなし集です。
(緑が丘図書館)
『まほうのバス』 中島和子/作,江田ななえ/絵,金の星社,913/ナ
バスは、おきゃくさまのいのちをあずかり、じかんどおりにはしることに、ほこりをもっていました。
でも、ふるくなり今日でいんたいすることになりました。
しごとがおわったよるに、いきたいところにいこうと、はしり出しました。
山のふもとでこぎつねをのせて、山のどうぶつたちものせて、山のむこうへしゅっぱつ!
とちゅうでバスはねんりょうがきれてうごけなくなってしまいました。
バスが、こぎつねをおくりとどけたいとお月さまにおいのりすると、ふしぎなことがおこりました。
よみおえると、こころがほっこりとあたたまるおはなしです。
(緑が丘図書館)
『ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん』 高岡昌江/文,篠崎三朗/絵,学研プラス
動物園の動物も、だんだん年をとって、おじいちゃん・おばあちゃんになります。
年をとると、食よくがなくなったり、目が見えなくなったり、動けなくなって、ねたきりになってしまう動物もいます。
この本は、動物のおじいちゃん・おばあちゃんたちのお話です。
年をとっても、若いころのように気高くいげんをもっているチンパンジーのおじいちゃんや、世話好きなおばあちゃんイルカなど、なんだか私たちの身近にいるおじいちゃん・おばあちゃんに似ているようです。
動物たちが、動物園で日々生活しているという事や、動物たちが歩んできた人生(?)に、おどろきや尊敬(そんけい)を感じます。
この本に出てくる、7頭のおじいちゃん・おばあちゃん動物の人生を振り返ってみましょう!(緑が丘図書館)
『ダンボールで作るおもしろ自動販売機』 大野萌菜美/監修, ブティック社
なんでもすきな物がでてくる自動販売機(はんばいき)があったら、わくわくしますね。
ジュースとか、アイスとか、おかしとか、みんなのまわりにはいろいろな販売機があります。
この本には、自動販売機の作り方が書いてあります。
ジュースの販売機だって、カプセルのだって、この本を見ながら、作ることができます。
いろいろ工夫して、自分の好きな物がでてくる、販売機を作ってみましょう!(緑が丘図書館)
『フランダースの犬』 ウィーダ/原作,いもとようこ/文絵,金の星社,E/イ
ベルギーのフランダース地方(ちほう)に、画家(がか)をゆめ見るネロという少年(しょうねん)と、犬のパトラッシュがすんでいました。
ネロのおとうさんとおかあさんは、ネロが2さいのときになくなってしまい、ネロはおじいさんにそだてられました。
おじいさんは、まいにち、村からとなり町までミルクをはこんで、すくないお金をもらい生活(せいかつ)をしています。
ネロとパトラッシュはおじいさんのてつだいをしながら、まずしいながらも、とてもしあわせにくらしていました。
けれど、そんなしあわせな日々もながくはつづきませんでした。
大人になってもわすれてほしくないせかいの名作(めいさく)が、いもとようこさんのかわいらしい絵とともに、とてもよみやすい絵本になっています。(緑が丘図書館)
『かわいいだけがウサギじゃない~むかしばなしのウサギたち』 福井栄一/著,技報堂出版,913/フ
現代では、可愛くてペットとして大人気のウサギ。そんなウサギが大活やくする昔話が3つ入っています。『ウサギとカメ』、『因幡(いなば)の白ウサギ』、『かちかち山』、どれもよく知られている話ですが、それぞれの話には意外な後日談がありました。
『ウサギとカメ』でカメに負けたウサギは他の動物にばかにされ、仲間のウサギからも冷たいあつかいをうけるようになります。復讐心(ふくしゅうしん)に燃えたウサギはカメにまた競争をもちかけることに。はたして今度こそウサギは勝てるのでしょうか!?
それぞれ昔話の原話とその後日談がえがかれ、ウサギたちのユニークで活き活きとしたすがたが楽しめます。(緑が丘図書館)
『月夜とめがね』 小川未明/作,高橋和枝/絵,あすなろ書房,E/オ
月のきれいな、しずかな夜のことです。おばあさんがひとり、はり仕事をしながら物思いにふけっていると、外の戸をコトコトたたく音がしました。そして「おばあさん、おばあさん」とだれかがよぶ声がします。おばあさんがのぞいてみると、外にいる男は“めがね売り”と名乗りました。はりに糸が通らずこまっていたおばあさんは大よろこびし、すぐにめがねを買いました。めがね売りが去った後、仕事がひとだんらくしもう休もうとしていると、またトントンと戸をたたく音がします。今日はお客さんがよく来るふしぎな夜だ、と思いつつ戸を開けてみると、そこには美しい女の子が立っていました。
“日本のアンデルセン”とよばれた小川未明の美しい夜のおはなしです。(緑が丘図書館)
『ともだちいっぱい リュックのりゅう坊』 工藤直子/作,長新太/絵,文渓堂,913/ク
りゅうの子どものりゅう坊(ぼう)は、リュックをしょっておでかけです。リュックの中には、サンドイッチと、水でっぽうと、バスタオルを入れました。
りゅう坊は、空をとんで、なかよしのわたぐもといっしょに、うみへゆきました。水でっぽうであそんでいると、くじらやいるかやたくさんのさかなたちがやってきました。「たつまきごっこだよっ!」とりゅう坊がいうと、「ぼくらもいれて」とみんながさけびました。ぐーるぐるぐる。りゅう坊もみんなも、大きくはやくまわりはじめました。
たのしさいっぱいの、りゅうの子どものりゅう坊のおはなしが、あと3つ入っています。ほかのおはなしでは、りゅう坊は、リュックになにをいれておでかけしたのでしょう?。(緑が丘図書館)
『子どものうちに知っておきたい! おしゃれ障害』 岡村理栄子/監著,少年写真新聞社,494/オ
テレビに出ているアイドルみたいに、お化粧(けしょう)をしたり、髪(かみ)をそめたり、ピアスをしたり、おしゃれしてみたいな~と思ったことはありませんか?でも、まわりの大人の人からは、「子どもだからダメ!」とか「体に良くない」とか言われてしまうかもしれません。
子どものころからお化粧をしていたら、本当に体に良くないのでしょうか?おしゃれをすることで、自分に自信が持てたり、明るい気持ちになったり、良いこともいっぱいあります。でも、化粧品で、はだがあれてしまうトラブルや、目が見えなくなるというような障害(しょうがい)もおこっているそうです。
本の題名「おしゃれ障害」というのは、おしゃれをすることで体におきるトラブルのことです。
この本を読んで、安全におしゃれを楽しむ、正しい知識を学びましょう!(緑が丘図書館)
『盲導犬不合格物語』 沢田俊子/文,学研,369/サ
盲導犬(もうどうけん)は、目の不自由な人の目となって、いっしょにくらします。
盲導犬の訓練(くんれん)を受けても、すべての犬が合格(ごうかく)できるわけではありません。いくら訓練の結果(けっか)がよくても、けいかい心が強かったり、自分の役目をわすれてよろこびすぎたり、むだぼえをしたりする犬は、盲導犬にはなれません。でも、盲導犬になれず不合格になっても、人のために活やくしている犬がたくさんいます。介助犬(かいじょけん)やマジシャンになって、人の心をいやしている犬もいます。
不合格犬が、それぞれの生き方に出会えて、自分らしく生きていることがよくわかります。(緑が丘図書館)
『おーばあちゃんはきらきら』 たかどのほうこ/さく,こみねゆら/え,福音館書店,913/タ
チイちゃんには、おばあちゃんとおーばあちゃんがいます。おーばあちゃんは、チイちゃんのひいおばあちゃんです。小さくて、しわがあって、目がうすいみどりいろのみずうみみたいにすきとおっていて、ほーほーってしゃべります。
チイちゃんは、やさしいおーばあちゃんがだいすき。「おーばあちゃんって、なんだか、まほうつかいのおばあさんみたい」とおもっています。それは、おーばあちゃんがふしぎなおはなしをきかせてくれたから。
みんなも、チイちゃんといっしょに、おーばあちゃんのふしぎな、すてきなおはなしをきいてみましょう!(緑が丘図書館)
『庭のマロニエ ―アンネ・フランクを見つめた木』 ジェフ・ゴッテスフェルド/ぶん,ピーター・マッカーティ/え,松川真弓/やく,評論社,E/マ
うら庭に立つ1本のマロニエの木は、170年も生きてきました。
小さかったマロニエは、根を広げ、空に枝をのばしました。
そのころ、マロニエは、生き生きと遊び、幸せではちきれそうな1人の少女を見るのが好きでした。
ある年、戦いが始まり、少女の一家は「隠れ家(かくれが)」でひっそりとくらすようになりました。少女は外に出られず、心の内を日記につづりました。
マロニエが語る少女は、アンネ・フランクです。アンネを見ていた、このマロニエの種やなえ木は、世界中におくられ、日本でも大切に育てられています。
高学年のみなさんに紹介(しょうかい)していますが、読んであげるなら、1年生くらいからおすすめの絵本です。(緑が丘図書館)
『動物園ものがたり』 山田由香/作,高野文子/絵,くもん出版,913/ヤ
まあちゃんは、お父さんとお母さんといっしょに動物園に来たけれど、ふたりがケンカばかりしているのでいやになってしまいました。そのため、自分からまいごになって、動物園のカバの前にひとり立っていました。カバを見ていたら、おじいさんとおばあさんにやさしく話しかけられました。
おじいさんは「ヒポポタマス」という楽しい言葉を教えてくれました。「ヒ・ポ・ポ・タ・マ・ス、ヒ・ポ・ポ・タ・マ・ス…」まあちゃんは、心の中で、くりかえし言ってみました。
この言葉は、カバのウメちゃんにも通じたようで、ウメちゃんは、まあちゃんのことを見てくれました。
まあちゃんは、ウメちゃんがすきになりました。まあちゃんやお父さん、お母さん、おじいさんやおばあさん、カバのウメちゃん、飼育員(しいくいん)さんも、「ヒポポタマス」というまほうのじゅもんで、やさしい気持ちになっていきます。(緑が丘図書館)
『ばけものつかい』 川端誠/作,クレヨンハウス,E/カ
とある、大きなおみせのごいんきょさまが、ほうこう人をつれてふるい大きなおやしきにひっこしてきました。ところがここは、ばけものがでる“おばけやしき”とうわさされています。
ほうこう人はにげてしまいましたが、ごいんきょさまは「おばけがなんだ」と気にしません。
そのよる、ごいんきょさまが、おやしきに一人でいると、せなかがぞくぞくしてきました。そして、にわのしょうじがスーッとひらき、ひょっこりと一つ目こぞうがかおを出しました。
落語(らくご)をもとにしたおはなしです。
ごいんきょさまはどうなってしまうの!?と思いきや、落語ならではのおもしろい展開(てんかい)がまっています。
こわいはずのおばけがかわいく見えてくるかもしれません。(緑が丘図書館)
『あつまれ!全日本ごとうちグルメさん』 ふくべあきひろ/文, あおのこうへい/絵,ロンズ新社,383/フ
今日は年に一度、日本全国のごとうちグルメさんが集まる日。
北は北海道のジンギスカン様、南は沖縄(おきなわ)のゴーヤーチャンプルー選手まで、47都道府県それぞれの味じまんのごとうちグルメさんが、ごとうち総本山にいるまんぷく様のもとをおとずれます。
おやつや食材に変身したり、各地の方言でしゃべりながらの大宴会(だいえんかい)で大さわぎ!
ユニークなキャラクターたちがおいしく楽しく都道府県のことを紹介(しょうかい)してくれます。
(緑が丘図書館)
『蒼とイルカと彫刻家』 長崎夏海/作,佐藤真紀子/絵,薬師寺一彦/協力,佼成出版社,913/ナ
一年生の夏にプールでおぼれてから、蒼(あお)の心の中に一頭のイルカが住むようになり、この心の中のイルカに、とくいな絵をかいて見せたり、話をしたりしていました。
三年生の夏休みに、消しゴムをけずって心の中のイルカ「ぼくのイルカ」を作り始めます。
図書館でイルカの本をかりた帰り道、雑木林(ぞうきばやし)の大きな木の根元に、とうめいなしずくの形をしたおき物をみつけました。
それを見つめていると、蒼の中のイルカがぐんと動き……。
「ぼくのイルカ」をなっとくするまで作りつづけるうちに、自分に自信(じしん)の持てなかった蒼が成長(せいちょう)していきます。
(緑が丘図書館)
『こぶたのピクルス』 小風さち/文,夏目ちさ/絵,福音館書店,913/コ
ピクルスはこぶたの男の子。
あるあさ、学校へいくピクルスに「ピクルスや。わすれものはないかい?」と、おかあさんがききました。ピクルスは「きょうかしょ、よし!ノート、よし!エンピツ、よし!ハンカチ、よし!わすれものは、ひとつもなし!」と大きなこえでこたえました!
おかあさんに手をふって、スキップをしながらでかけたピクルスですが、とちゅうで、おとうさんや牛(うし)のぎゅうにゅうやさんや、ロバのパンやさんたちにあって、つぎつぎにようじをたのまれます。
みんなのようじをすませて、とくいなきもちのピクルス。
でも、いちばんたいせつなことを、わすれてしまっているようです……。
『月のえくぼを見た男 麻田剛立(あさだごうりゅう)』 鹿毛敏夫/著,関屋敏隆/画,くもん出版,289/ア
みなさんは、望遠鏡で月を見たことがありますか?
江戸時代、剛立(ごうりゅう)は、5才で縁側(えんがわ)に入るかげの場所が変化するのを見て、「太陽がぼくの家のまわりを回っている」と気がつきました。
11才で、昼間は庭で棒(ぼう)を立てて、かげの長さの変化を記録し、夜は夜空にうかんだ月がどの星座の間を移動していくのかを記録しました。
それからも剛立は、太陽と月の観測を日々積み重ね、日食や月食がおきるのを予測して、まちの人々に知らせました。
望遠鏡をのぞいて、月の様子をスケッチした初めての日本人、天文学者「麻田剛立(あさだごうりゅう)」の伝記です。(緑が丘図書館)
『かき氷 天然氷をつくる』細島雅代/写真,伊地知英信/文,岩崎書店,588/ホ
つめたくておいしいかき氷。
氷は、今でこそ冷凍庫(れいとうこ)で手軽に作れますが、昔は、冬に作った氷を
夏までほぞんして使っていました。
それは、天然氷(てんねんごおり)とよばれるとくべつな氷です。
こんにち、この天然氷を作る氷屋さんは、日本でとても少なくなりました。
時間と手間をかけて作りあげた天然氷で作るかき氷は、どんな味がするのでしょうか?
古くから受けつがれる天然氷作りを、たくさんの写真でかいせつしています。(緑が丘図書館)
『皇帝にもらった花のたね』デミ/作・絵,武本佳奈絵/訳,徳間書店,E/デ
むかしむかし、いろとりどりの花であふれているくにがありました。
皇帝(こうてい)はあとつぎをきめるため、くに中の子どもに花のたねをくばり、そのたねをたいせつにそだてて、1年ごに見せにくるようおふれをだしました。
花をそだてるのが大すきな男の子ピンは、もらった花のたねを“だれよりもきれいにさかせるぞ!”と、はりきってそだてはじめました。
ところが、どんなにおせわをしても、いっこうにたねからめはでてきません。
とうとう1年がたち、皇帝とのやくそくの日をむかえます。
ほかの子どもが、じぶんでそだてたうつくしい花をもってきゅうでんにむかう中、ひとり、めのでていないはちをもったピンは、どうなるのでしょうか?(緑が丘図書館)
『よむプラネタリウム 夏の星空案内』 野崎洋子/作, 中西昭雄/写真 ,アリス館,433/ノ
夜空を見上げると、星がかがやいて見えます。
でも、家の周りが明るかったり、くもっていて星が見えない日もありますね。
この本は、“よむプラネタリウム”です。
本を開くと、いつでも、多くの星がまたたいていて、プラネタリウムで星を見ているような気持ちになります。
夏の星座(せいざ)や、ペルセウス座流星群(りゅうせいぐん)など、星の名前や星座の形、見える方向や見える時間などを、やさしく教えてくれます。
この本で、星について楽しく学んでから、夜空を見上げ、星や星座を探してみましょう!(緑が丘図書館)
『根っこのえほん1 おいしい根っこ』 中野明正/編著,小泉光久/文,堀江篤史/絵,大月書店,471/ネ
わたしたちは、いつも、「根っこ」を食べています。
「根っこは食べられないんじゃないかな」と思いましたか?
さつまいもやにんじん、じゃがいも、大根も、植物の「根っこ」です。
わたしたちは、植物の「実」や「葉」、「くき」を食べたり、「花」や「根っこ」も食べています。
この本は、いつも食べているにんじんや大根など、根菜類(こんさいるい)について書かれています。
わたしたちは、植物の「根っこ」のどの部分を食べているのでしょう?
本をじっくり読んでみましょう!(緑が丘図書館)
『だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ』安房直子/作,ひがしちから/絵,偕成社,913/ア
だんまりうさぎはひとりぼっちで、おともだちがいませんでした。
あるあさ、おしゃべりうさぎがやってきて、おともだちになりました。
だんまりうさぎのはたけに、大きなかぼちゃができました。
どうやってたべようかな?だんまりうさぎはとってもいいことをおもいつきました。
「7月30日にかぼちゃのおりょうりを、たべにきてください。
おともだちも、たくさんつれてきてください。」とおしゃべりうさぎに、てがみをかきました。
この日は、だんまりうさぎのおたんじょうびなのです。
さあ、おともだちはあつまってくれるのでしょうか?(緑が丘図書館)
『銀のらせんをたどれば』 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/作 市田泉/訳 佐竹美保/絵,徳間書店,933/ジ
“神話層(しんわそう)”とは、地球で生みだされる、あらゆる物語や信仰(しんこう)、伝説、神話、希望などでできていて、地球の周りをいくつもの層になっておおっています。
祖父から神話層の話を聞いたハレーは、とても心ひかれました。
あまりに夢中になりすぎたハレーは、祖母をおこらせてしまいます。
ハレーはアイルランドに住むおばの家に連れて行かれ、そこでくらすことになりました。
初めて出会う親せきの子どもたちと仲良くなったハレーは、神話層に入りこんで、物語からアイテムを取ってくるというゲームに参加することになります。
しかし、ゲームが気に食わないジュダーおじさんに追われ、神話層のらせんをたどってあちこちにげ回ることに。
ハレーは無事に現実の世界へもどれるのでしょうか!?
星座(せいざ)の起源(きげん)となったものたちが物語のいろいろな場面にでてきて活躍(かつやく)します。
現実の世界と神話の世界をめぐるファンタジーです。(緑が丘図書館)
『古道具ほんなら堂 ~ちょっと不思議あり~』 楠章子/作 日置由美子/画,毎日新聞社,913/ク
優子(ゆうこ)は、このごろわがままばかりのおばあちゃんが苦手です。
おふろにも、せっけんのにおいがちがうと言って、ちゃんと入ってくれません。
まごのこともわからなくなってしまったおばあちゃんと、どうすればまたなかよくなれるのか、優子はとまどっていました。
そして、おばあちゃんに気持ちよくおふろに入ってもらうため、おばあちゃんのお気に入りのせっけんをさがしもとめて、古道具屋ほんなら堂(どう)へたどり着きます。
古道具にはふしぎな力が宿っている!?
こまったとき、少しだけ勇気(ゆうき)を出せば、店主の橙花(とうか)さんがちょっとだけ力をかしてくれます。
古道具屋のおばあさんと不思議(ふしぎ)な古道具の5つのおはなしです。(緑が丘図書館)
『ゴリラでたまご』 内田麟太郎/作 日隈みさき/絵,WAVE出版,913/ウ
ライオンのおじいさんは、さかみちの下で大きなたまごをみつけました。
「あなたは、なんのたまごなの?」とたずねると、たまごは「たまごじゃない、ゴリラだ」とこたえました。
そこへ、たまたまあるいてきたゴリラは、「でっかいたまごですな」といいました。
ライオンのおじいさんは「ゴリラさんです」というけれどが、ゴリラには、たまごにしかみえません。
そのつぎに、サイが「これはなんだ?」ときくと、たまごはかわいいこえで「あたいうさぎだよ」といいます。
それをきいたライオンのおじいさんとゴリラとサイはびっくりしました。
ことばあそびもたのしいゆかいなおはなしです。(緑が丘図書館)
『テオの「ありがとう」ノート』 クロディーヌ・ル・グイック=プリエト/著,PHP研究所,953/ル
ある朝、テオは「決心」した。
それは「ありがとう」って言わないこと。
障がいのあるテオは、何をするにもまわりの手助けが必要になる。手助けしてもらったら、「ありがとう」って言う。だから、ふつうの人の何倍も何倍も「ありがとう」って言うことになる。
ある日、こんなのは不公平だし、もううんざりだ!と思い、「ありがとう」を言わない「決心」をしたのだ。
このテオの「決心」はテオ自身やまわりの人々をすこしずつ変えていくことになる。
自分の障がいを受けとめ、自立していこうともがくテオ。
まわりに「ありがとう」と言うだけでなく、「ありがとう」と言われる喜びを知るようになってゆく……。
(緑が丘図書館)
『グッディさんとしあわせの国』 ルース・エインズワース/作,岩波書店,933/エ
むかし、海べの家に、ベンという男の子が、住んでいました。
ベンとおねえさんのマーサは、海のむこうに見えるはまべを、「しあわせの国」とよんでいました。
ベンは、おばあちゃんからもらった“グッディさん”という小さな木の人形がお気に入りで、どこへ行くにもグッディさんといっしょでした。
ある日のこと、ベンが、石がきの上でグッディさんと「しあわせの国」をながめていると、とつぜん、グッディさんは波にさらわれて海の中へ……。
ベンは、しょんぼりふさぎこんでしまいました。
しばらくして、カモメがマーサに、グッディさんは「しあわせの国」にいると教えてくれました。
その日から、マーサは毎ばんグッディさんの話をベンに聞かせるのでした。
この本には、“海”がでてくるすてきなお話があと2つあります。
(緑が丘図書館)
『しあわせないぬになるには』 ジョー・ウィリアムソン/作・絵,徳間書店,E/ウ
おうちでいぬをかっている人はいますか?
「このいぬをかう!」と、きめたときのことを、おぼえていますか?
わたしたちが、かいたいいぬをえらぶように、いぬもじぶんのすきな“かいぬし”をえらんでいるみたいです。
かいぬしであるにんげんを、どうやってよろこばせるかなど、しあわせないぬの“ぼく”がこっそりおしえてくれます。
(緑が丘図書館)
『さすらいの孤児ラスムス』 アストリッド・リンドグレーン/作,尾崎義/訳,岩波書店,949/リ
孤児(こじ)のラスムスは、9歳(さい)の男の子。
ある夜、こっそり村の孤児院(こじいん)をにげ出したラスムスは、風来坊(ふうらいぼう)オスカルと出会い、一緒(いっしょ)に旅をすることになります。
陽気なオスカルは、アコーディオンを奏(かな)でながら歌をうたってお金をかせぎ、ラスムスはオスカルを手伝いながら旅を続けていました。
そんな旅の途中(とちゅう)、ラスムスは強盗(ごうとう)現場を見てしまい、なんと、ふたりは犯人に命をねらわれることに!
さあ二人は無事ににげることができるでしょうか?
(緑が丘図書館)
『おいしいごはんができるまで1 お米からそだてるおにぎり』 真木文絵/文,石倉ヒロユキ/絵,偕成社,596/マ
遠足(えんそく)や運動会(うんどうかい)などのおべんとうの定番(ていばん)“おにぎり”
“おにぎり”は「ごはん(お米)」だけでできているのではなく、塩をまぶしたり、のりをまいたり、中にうめぼしを入れたりしますね。
この本では、“おにぎり”のもとになっている食べ物が、どんなふうにできているのかをしっかりと学ぶことができます。
“おにぎり”についての豆知識(まめちしき)やにぎり方ものっていますよ!
この本を読んで、とびきりおいしい“おにぎり”を作ってみましょう!
(緑が丘図書館)
『和菓子(わがし)のほん』 中山 圭子/文,阿部 真由美/絵,福音館書店,596/ナ
こどもの日にはかしわもち、おひがんにはおはぎ。
日本どくとくのお菓子(かし)である和菓子(わがし)には、日本人の、しぜんをあいするきもちや、うつくしさをかんじる心(こころ)がやどっています。
春(はる)・夏(なつ)・秋(あき)・冬(ふゆ)のきせつのうつりかわり、人々のゆめやねがいをいろやかたちで工夫してうつくしくひょうげんする和菓子(わがし)。
いろいろなしゅるいの和菓子(わがし)をしょうかいし、ざいりょうやつくりかた、れきしまではばひろく、わかりやすくかかれたえほんです。
(緑が丘図書館)
『やまんば山のモッコたち』 富安陽子/作,降矢奈々/画,福音館書店,913/ト
モッコというのは、人間ではなく、動物ともちがう変わり者の生き物たちのこと。
啓太が住む村の北側には、そんなモッコ達が住むやまんば山がありました。
ある日、啓太はキツネに案内されてやまんば山へ入っていきます。
そこで出会ったのはやまんばの娘、まゆでした。
やまんば山では、やまんばにかっぱ、天狗(てんぐ)、雪女…大きな鬼(おに)から名もない小さな生き物まで、山に住むたくさんのモッコ達が活躍(かつやく)します。
(緑が丘図書館)
『生きものビックリ食事のじかん』 スティーブ・ジェンキンズ&ロビン・ペイジ/作,佐藤見果夢/訳,評論社,E/ジ
生きものはみんな食べたり食べられたりして生きています。
だから弱い生きものは、自分たちが食べられないようにかくれたり、安全な場所で卵(たまご)をうんだり子どもを育てたりします。
生きものたちはどうやって魚をつかまえて食べるのか、どうやって卵(たまご)を守るのかなどをのぞいてみると、そこにはふしぎなことがいっぱいです。
切り絵でえがかれた生きものたちを見るのも楽しい絵本です。
(緑が丘図書館)
『ツツミマスさんと3つのおくりもの』 こがしわかおり/作,小峰書店,913/コ
ツツミマスさんのしごとは、「つつむこと」です。
なんでもすてきにつつむことができます。
“すてき”にプレゼントをつつんでもらいたくて、いろいろなおきゃくさまがツツミマスさんのおみせにやってきます。
ツツミマスさんは、おきゃくさまのたいせつな?おくりもの”を、どんなふうにつつむのでしょう?
おきゃくさまはよろこんでくれるでしょうか?
プレゼントをあけるときってワクワク・ドキドキしますね。
この本でもそのワクワク・ドキドキをかんじることができますよ!
(緑が丘図書館)
『食べて始まる食卓のホネ探検 ゲッチョ先生のホネコレクション』 盛口満/文・絵,少年写真新聞社,481/モ
朝ごはんのアジの干物、おやつのフライドチキン、夜ご飯のかれいの煮つけ。
おいしく食べた後には何が残りますか?
そうです、ホネが残ります。
同じホネでも、生き物によって形やつくりが全然ちがいます。
この本は、それぞれのホネの細かい部分まで正確に描かれています。
アジの干物やフライドチキンのホネもすぐには捨てないでください!
これからは、食べ終えて残ったホネを、じっくり調べてみたくなるかもしれません。
この本でホネをよく観察してみましょう!
(緑が丘図書館)
『いたずらおばあさん』 高楼方子/作,千葉史子/絵,フレーベル館,913/タ
エラババ先生は84さいのえらいえらい洋服研究家です。
ヒョコルさんは68さいで、エラババ先生のおはなしを聞きに通っています。
ヒョコルさんがエラババ先生の家へ遊びにいくと、先生が発明した「わかくなる服」を見せてくれました。
その服を1まいきると1さいわかくなります。そこでエラババ先生は76まい、ヒョコルさんは60まいきると、ふたりはなんと8さいの女の子に!
8さいの女の子になったふたりのおばあさんは、おぎょうぎの悪い大人をこまらせようといたずらを考えます。さあどんないたずらでしょうか。
(緑が丘図書館)
『とりになったきょうりゅうのはなし』 大島英太郎/さく,福音館書店,E/オ
きょうりゅうのかせきを、みたことがありますか?
きょうりゅうは、おおむかしにぜつめつしたといわれています。
でも、じつはぜつめつしたのはおおきなきょうりゅうたちだけで、つばさをもった、とぶことのできるちいさなきょうりゅうたちはいきのこりました。
そして、これらのきょうりゅうは、「とり」となって、いまでもこのちきゅうじょうにいきています。
おおむかしのきょうりゅうのすがたから、いまのとりになるまでがわかりやすく、きれいなえでかかれたえほんです。
(緑が丘図書館)
『電子顕微鏡で見る超ミクロの世界』 矢口行雄/著,誠文堂新光社,460/ヤ
「手にはばい菌がついているのでよく洗いましょう」
だれもが一度は言われたことのある言葉ではないでしょうか。
でも、手の上にばい菌は見えないのに、本当についているの?
ばい菌を見るためには、0.001mmというとても小さいものを見る器具が必要です。
この本では、学校の授業で使うけんびきょうよりもっともーっと小さいものが見える、特別なけんびきょうを使っています。
ふだんよくみかける、昆虫や植物などの知らない姿が見られますよ。
いざ、超ミクロの世界へ!
(緑が丘図書館)
『美術館にもぐりこめ』 さがらあつこ/文,さげさかのりこ/絵,福音館書店,706/サ
美術館にいったことはありますか?
有名な画家のかいた絵やちょうこくの像などがならんでいます。
この絵やちょうこくはどうやってならべられたとおもいますか?
美術館の人ってどんな仕事をしているのでしょうか?
この本では、美術館にもぐりこんだどろぼうたちが、美術館の仕事やわたしたちの知らない美術館の“うらがわ”を紹介してくれます。
さて、どろぼうたちはどうなるのでしょう?!
(緑が丘図書館)
『くれよんがおれたとき』 かさいまり/さく,北村裕花/絵,くもん出版,E/キ
わたしとゆうちゃんは大のなかよし。
しゃせいのしゅくだいをしに、ゆうちゃんがわたしのうちにきた。
ゆうちゃんは、わたしのあたらしいたいせつなくれよんをおってしまった。
そして、あたらしいくれよんをもってきて「これ、かわりにつかって。」といったけれど、 わたしは、ありがとうといえなかった。
ゆうちゃんとは、そのあとはなしもしていない。
あるひがっこうで、わたしはどんなにゆうちゃんを、こまらせていたのかがわかった……。
なかよしのともだちとのすれちがいや、なかなおりがえがかれたえほんです。
(緑が丘図書館)